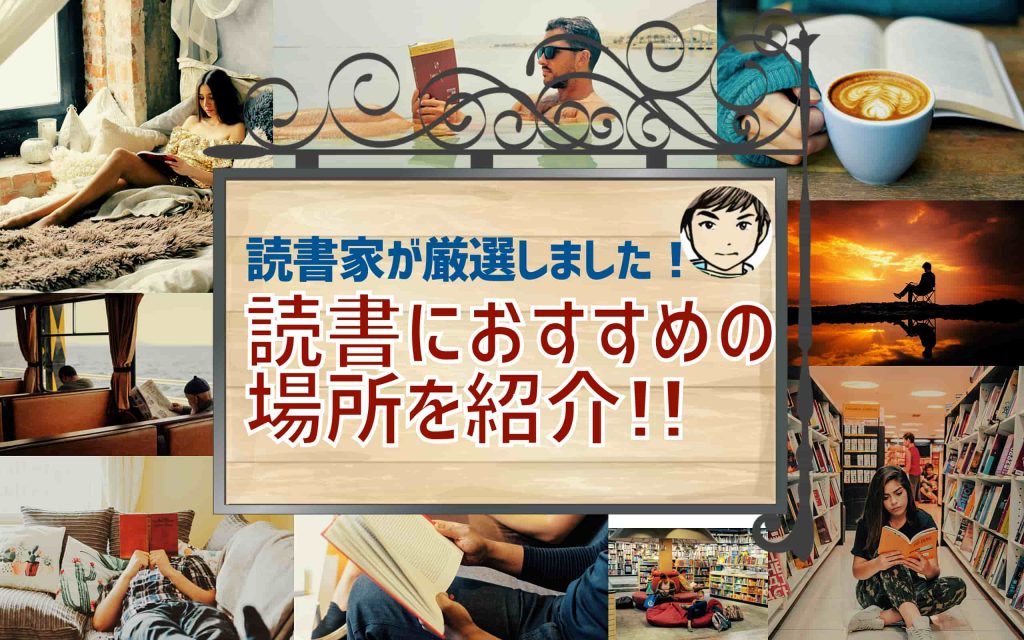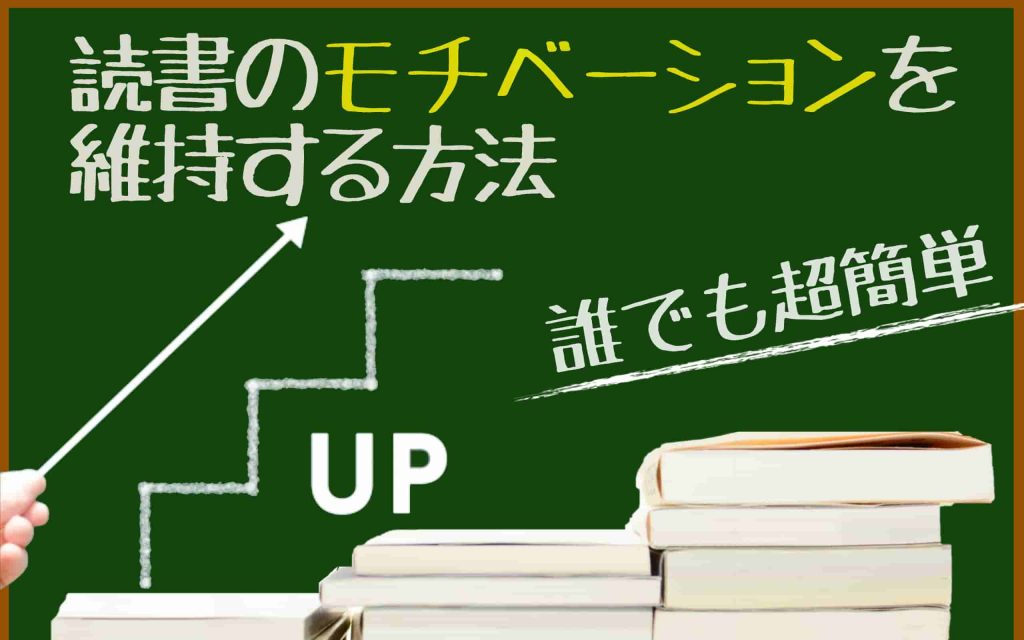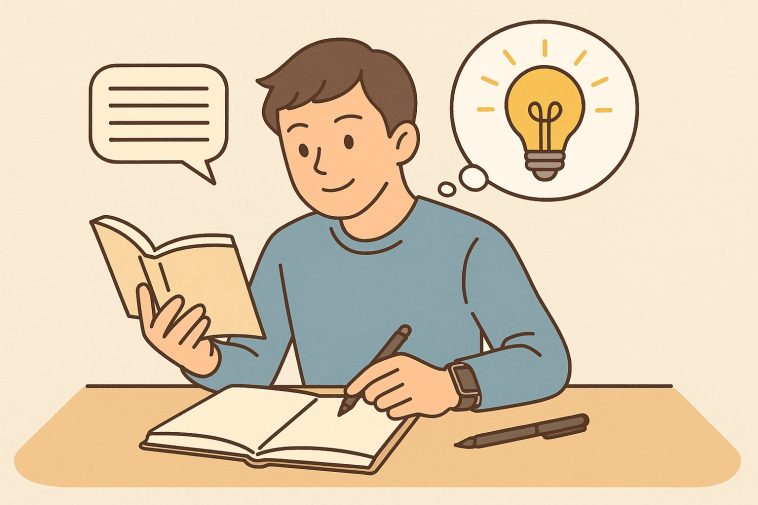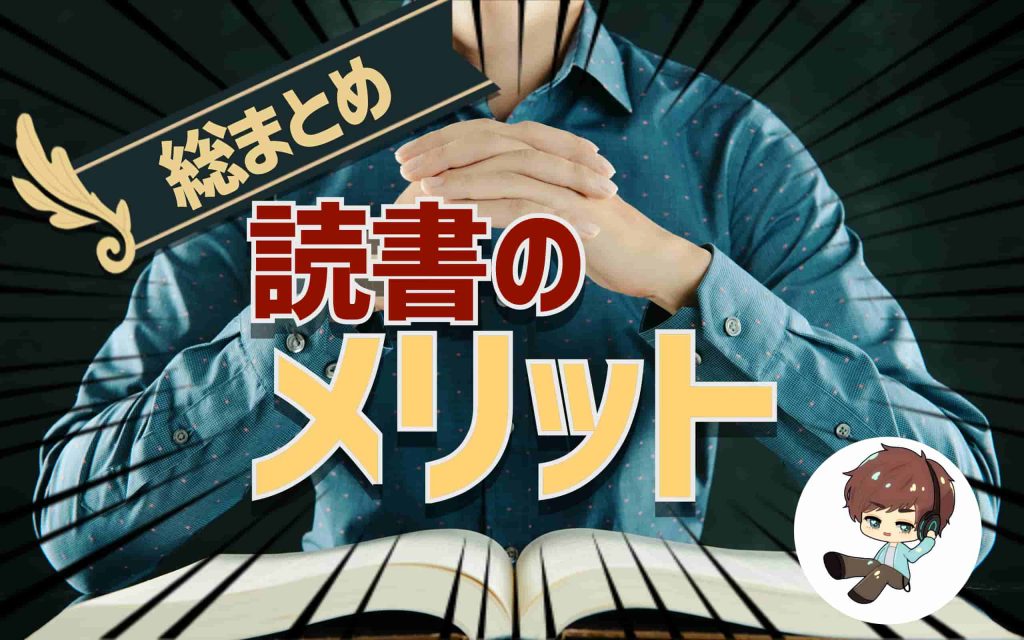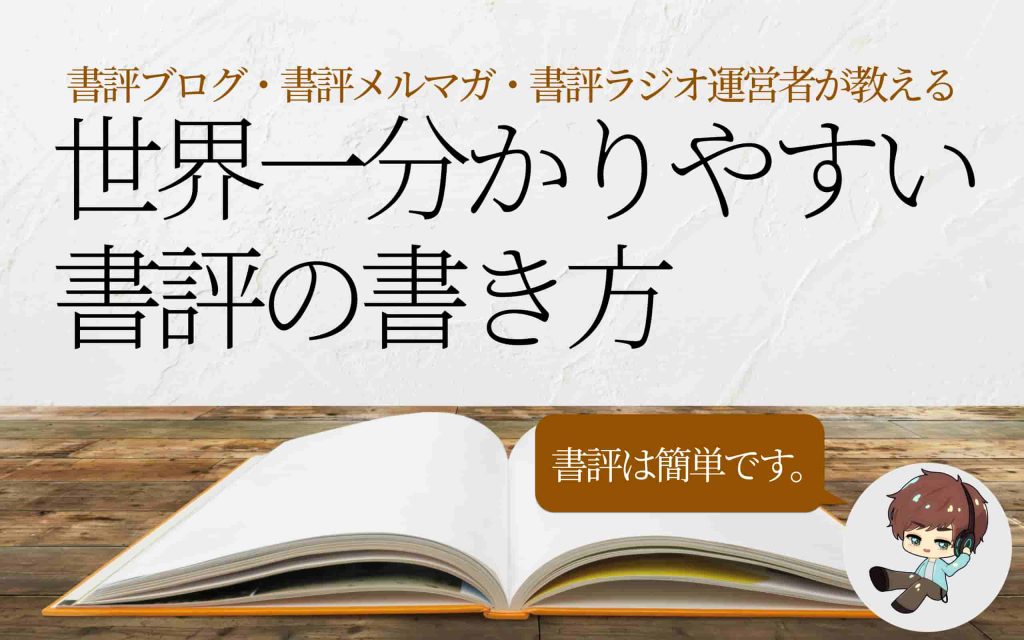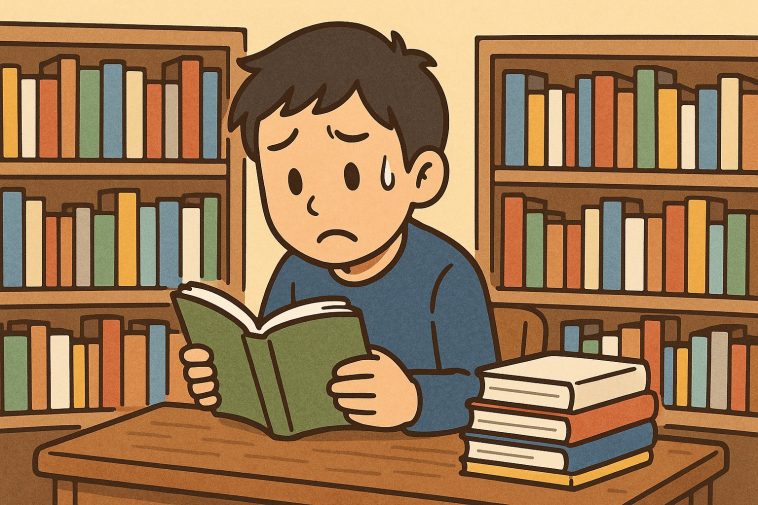「読書ノートを書いてみたけど、全然続かない…」
そんなふうに感じたことはありませんか?実は、僕もかつては同じように悩んでいました。
本を読むのは好きなのに、それを記録しようとすると手が止まってしまう。手帳を買っては三日坊主…を何度繰り返したことか。
でも、今では自然と読書ノートが続いています。
しかも、書く時間を意識せずとも習慣になっているんです。
この記事では、僕が「読書ノートが続かなかった理由」と、どんな工夫でそれを乗り越えたのかを体験ベースでご紹介します。
読書記録が苦手だった方でも、きっと「これならいけるかも」と思えるヒントが見つかるはずです。
聞く・話す!おすすめの音声体験アプリ2選!
| アプリ | 特徴 |
|---|---|
 | Castalk AI相手に気軽に練習!リアルな雑談体験ができるアプリ! |
 | Audible Amazonが提供する“耳で聴く読書”を楽しめるオーディオブックのサブスクサービス |
なぜ読書ノートは続かなかったのか?
まず最初に振り返っておきたいのは、「そもそもなぜ続かなかったのか?」ということです。
僕が感じていた主な理由は、次の3つです。
1. 毎回「しっかり書こう」としすぎていた
「せっかく読んだんだから、ちゃんと感想を書かないと」
「役に立つポイントを整理してまとめなきゃ」
そんなふうに力んでしまうと、書き出すハードルが一気に高くなります。
読書後に疲れていても「ちゃんと書かないと意味がない」と思い込んでいたのも、続かなかった理由のひとつです。
2. フォーマットを決めすぎていた
テンプレートや構成を完璧に決めてから始めると、逆にそれが枷になります。
「今日はポイントが3つもない」「名言がないから埋まらない」と、書けない理由ばかりが浮かんでしまうんですね。
3. 誰にも見られないことでモチベが下がる
意外なことかもしれませんが、僕の場合「誰にも見られない」という状況がモチベーションを下げていたようです。
完全に自分のためだけに書くことが、思っていたより難しかったんですね。
続いたのは「人に見られる前提」の記録だった
そんな僕でも、自然と読書記録が続いたきっかけがあります。
それが、「人に見られる場所で記録する」ことでした。
たとえば、以下のような方法です。
- Twitterで感想を1ツイートにまとめて投稿
- 読書ブログで印象的だったポイントだけ記録
- 音声アプリで1分だけ要点を録音して公開
これらはすべて、内容が完璧じゃなくても誰かに伝わることを前提としています。
「気軽だけど誰かが見る可能性がある」という緊張感が、いい意味で自分を動かしてくれたんです。
逆に「公開前提」にすることでラクになった
不思議なもので、「見せる前提」になると内容を深掘りしようとしなくなります。
むしろ、「この本で自分が一番心を動かされたところはどこか?」を1つだけ拾えばいい。
それだけで十分、立派なアウトプットになるんだと気づいてからは、記録がどんどんラクになりました。
読書記録を「公開前提」でゆるく続けるコツ
「読書ノートをつけよう」と思っても、完璧を目指して挫折してしまった経験はありませんか?
実は、読書記録を続ける最大のコツは「公開前提で、ゆるく書くこと」にあります。
完璧じゃなくていい。1行でもいい。
- 読んだ本の感想を1行だけX(旧Twitter)にポストする。
- 日付と一緒に「面白かった」とメモアプリに残す。
- 読書アプリで★をつけて一言レビューする。
それだけで十分なんです。
「ちゃんと書こう」と思うほど筆が止まり、「これでいい」と思えたとき、記録はスッと日常に馴染みます。
公開前提は“続ける”ための最強の武器
なぜ公開前提がいいのか?
それは、「誰かが見るかもしれない」という意識が、自然とあなたの記録に芯を通してくれるからです。
とはいえ、バズらせる必要なんてありません。
- 本のタイトル+刺さった一文だけ
- 自分の棚に並べる感覚で投稿
- “未来の自分”に宛てたメッセージとして書く
読書メモを「誰かと共有できる財産」として残すことで、記録が“作業”から“表現”へと変わっていきます。
非公開でも「誰かに読ませる気」で書いてみる
もちろん、SNSでの発信に抵抗がある方もいるでしょう。
でも非公開であっても、“誰かに話すつもりで”書くだけで、アウトプットの質はガラリと変わります。
「友達に紹介するとしたらどう言うか?」
「ブログ記事にするとしたら、何を強調するか?」
そんな風に、読者を仮想することで、記録のモチベーションが湧いてきます。
読書ノートは“自己対話”の場
読書ノートをつけるとき、誰かに見せる前提で書くのも良いですが、もう一つ大切なのが「自分との対話の場」として活用することです。
「何を感じたか」を書くだけでOK
本の内容を要約しなくても構いません。
「このセリフ、今の自分に刺さった」「著者の視点にモヤっとした」そんな心の動きこそ、読書ノートに残すべき宝物です。
ときには、まとまらない思考が並ぶだけの日もあります。
でも、それで十分。あとで読み返したとき、「あの頃の自分」の温度がそこに残っているからです。
読書ノートは“未来の自分”への手紙
人は時間とともに変わります。考えも、感じ方も、価値観も。だからこそ、過去の自分が何を読んで、何を思ったのか。
それを記録しておくことは、未来の自分に向けた“思考のログ”になります。
5年前に読んだ同じ本を、今読み返すと印象がガラリと変わる。
そんな経験はありませんか?
読書ノートは、読書そのものを“二度楽しむ”ためのツールでもあるのです。
書けば読む、読むからまた書きたくなる
ノートをつけていると、不思議と「もっと読みたい」と思えるようになります。
記録を残すことで、読書が点ではなく、線になってつながっていくからです。
- 過去に読んだ本との関連性
- 繰り返し出てくるテーマやキーワード
- 自分の内面にある“問い”の変化
こうした流れを可視化できるのが、読書ノートの面白さ。
単なる読書記録が、自分自身の成長記録へと変わっていきます。
読書ノートは「雑でもOK」
最初は箇条書きで十分です。
むしろ、書きたいときに、書きたいことだけを書く。それくらいのラフさが、長く続けるためのコツ。
私もかつて、読んだ本のすべてを要約しようとして挫折したことがあります。
でも今は、思いついた言葉をスマホのメモにポンと書き留めるだけ。それでも読み返すと、そのときの気づきが鮮明に思い出せるんです。
書くことが目的じゃない、「読むこと」が主役
読書ノートはあくまで“読書を楽しむための補助線”。
書くために読むのではなく、読んだ感動や思考を残したいから書く。
だから、途中でノートが止まってもいいし、飛び飛びでも気にしない。
「続いていること」こそが何よりの成果です。
1行だけでも立派な記録
たとえばこんなメモでも、十分価値があります。
- 「この一節、泣きそうになった」
- 「まさに今の自分に必要な言葉」
- 「〇〇さんにも読んでほしいかも」
形式にとらわれず、まずは「書いて残すこと」から始めましょう。
肩の力を抜いて、気軽に、自分のペースで。それが習慣になる第一歩です。
SNSでつながる読書仲間ができたら理想
一人で読む読書も楽しいけれど、誰かと共有できると、世界はぐっと広がります。
- 「読んだ本」をSNSでつぶやいてみる
- 「この本、心に刺さった」
- 「〇〇ページの言葉がすごく良かった」
そんな感想をX(旧Twitter)やInstagramのストーリーズでポロっと投稿するだけでも、意外と反応があるものです。
私も最初は恥ずかしかったのですが、読書アカウントを作って何気なく投稿してみたところ、
「その本、気になってました!」「私も最近読みました」
といった声が届き、気づけば“読書つながり”のフォロワーが増えていきました。
共感が、新しい読書のモチベーションに
共通の本を読んでいたり、知らなかった名著を教えてもらったり。
SNSでのやりとりは、読書のモチベーション維持にとても役立ちます。
特に、自分と似た読書傾向の人を見つけられると「この人のおすすめ本は間違いない」と、選書の幅も広がっていきます。
無理に発信しなくてもOK
もちろん、「読むだけ」「見るだけ」でも大丈夫。
気になる人の投稿をのぞくだけでも、読書の世界はどんどん広がります。
SNSの良さは、“距離感を自分で選べること”。
読む、書く、つながる。そのバランスを自分なりに調整しながら、読書の楽しみを深めていきましょう。
まとめ:習慣化の最大のコツは“記録しすぎないこと”
読書を習慣にするうえで、一番の落とし穴は「ちゃんと記録しなきゃ」という思い込みです。
感想もページ数も、きっちり残そうとすると、かえって読むこと自体が億劫になってしまいます。
大事なのは、完璧を目指さず、軽く続けること。「一言メモ」や「チェックをつけるだけ」でも十分です。
気楽に構えることで、読書はもっと日常に溶け込んでいきます。