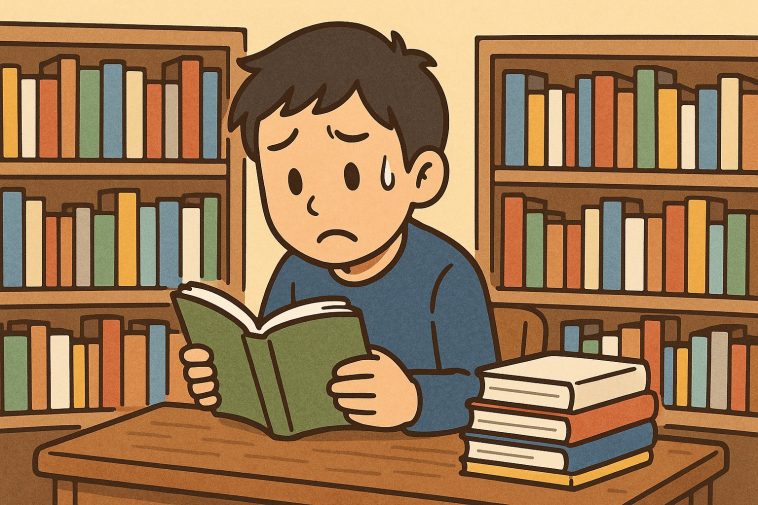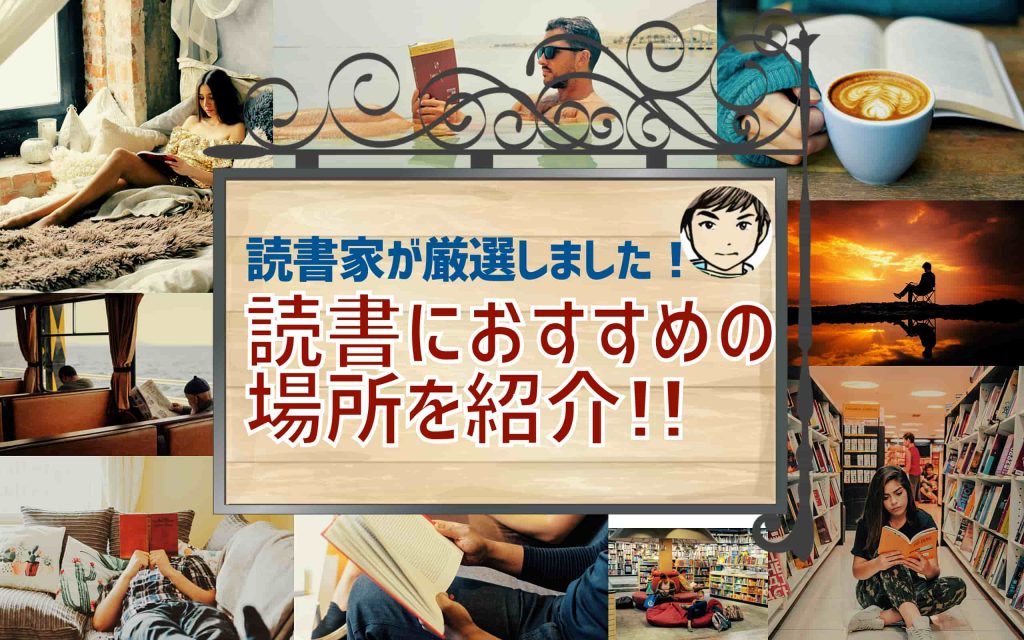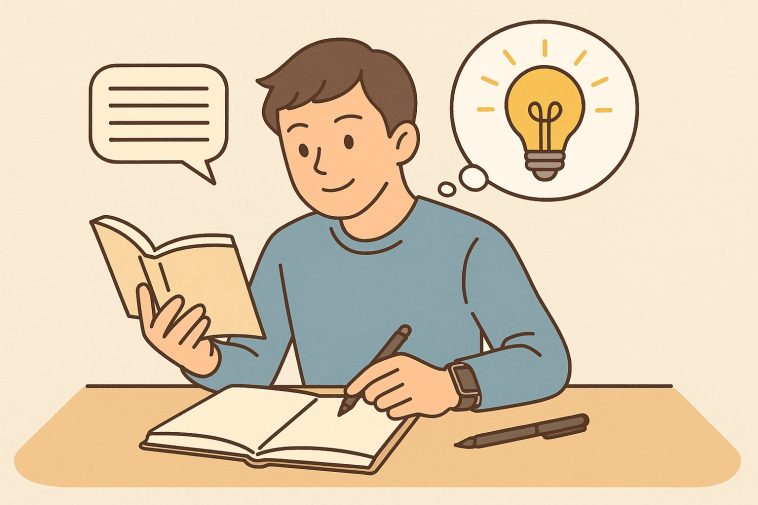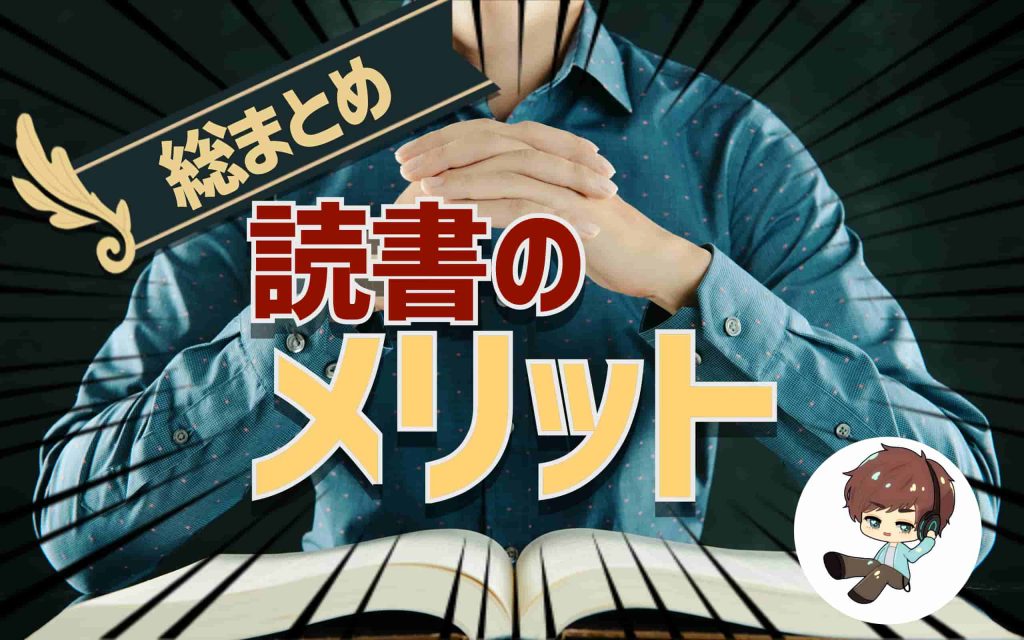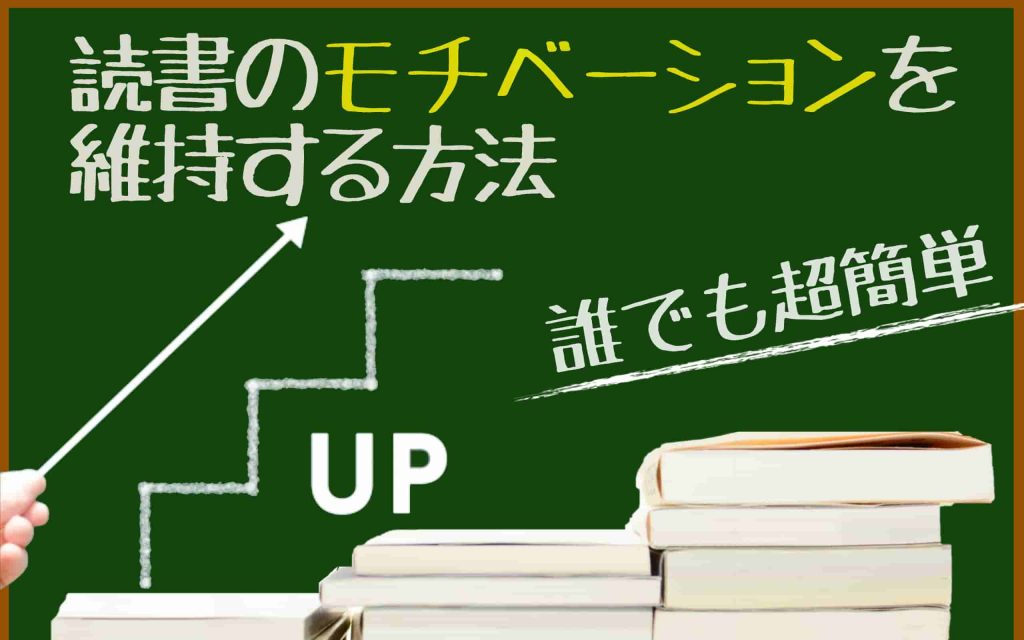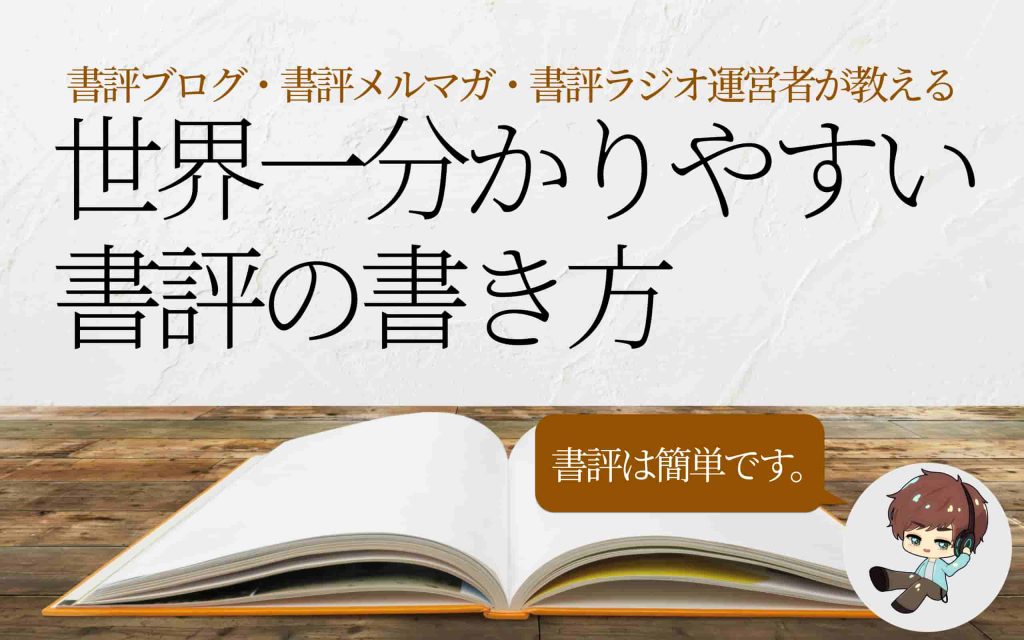この記事では「忙しくて読書の時間がとれない」という悩みを抱えている方に向けて、私自身の体験を交えながら、無理なく読書時間を確保する方法をご紹介します。
読書は「時間がある人だけの贅沢」ではありません。ちょっとした工夫で、どんなに忙しくても日常に取り入れられる習慣です。
聞く・話す!おすすめの音声体験アプリ2選!
| アプリ | 特徴 |
|---|---|
 | Castalk AI相手に気軽に練習!リアルな雑談体験ができるアプリ! |
 | Audible Amazonが提供する“耳で聴く読書”を楽しめるオーディオブックのサブスクサービス |
読書時間がとれない理由を知ろう
「本を読みたいのに、なかなか時間が作れない…」と感じる方は多いのではないでしょうか。
実は、読書時間が確保できない理由は人によってさまざまですが、大きく分けると 「優先順位」「隙間時間の使い方」「環境づくり」 の3つに集約されます。
ここでは、それぞれの理由を具体的に見ていきましょう。
日常の優先順位が読書以外に偏っている
私たちの毎日は、仕事・家事・SNSチェックなど「やらなければならないこと」であふれています。
気づけば、自由時間は動画やゲームに使ってしまい、読書が後回しになりがちです。
これは「本を読むのはいつでもできる」という意識が働いて、優先順位が下がっていることが原因です。
移動・休憩時間を活かせていない
通勤・通学やちょっとした休憩の時間は、実は読書にとても向いています。
たとえば、電車に揺られている30分間をスマホのニュースアプリで流し読みしてしまうのと、電子書籍で1章分を読むのとでは積み重ねが大きく変わります。
「小さな時間を読書にあてられていないこと」 が、まとまった時間がないと感じる大きな要因です。
集中できる環境づくりができていない
読書は静かな集中が必要ですが、スマホの通知や周囲の雑音に邪魔されると、思ったより進みません。
結果的に「せっかく時間を作ったのに集中できなかった」となり、やる気をなくしてしまうことも。
このように環境が整っていないと、時間を確保しても「読んだ気になれない」感覚に陥りがちです。
読書時間を確保する第一歩は、「なぜ読めないのか」を明確にすることです。
自分に当てはまる理由を把握すれば、次のステップで紹介する「時間を作る工夫」がぐっと効果的になります。
毎日のスケジュールに小さな読書時間を組み込む

「まとまった1時間を取らないと読書できない」と考えると、どうしても難しく感じてしまいます。
しかし実際は、1日10〜15分の積み重ねでも1か月で数冊の本を読み終えることができます。
ここでは、生活の中に自然に読書を組み込む方法を紹介します。
朝の15分を「読書タイム」にする
朝は頭がすっきりしていて集中しやすい時間帯です。
起床後すぐにスマホを見る代わりに、本を1章だけ読む習慣をつけると、それだけで月に数冊のペースが実現できます。
ポイントは「時間を区切る」こと。15分だけ、と決めることで無理なく続けられます。
就寝前のリラックスタイムに読書を入れる
寝る前の30分を読書にあてるのもおすすめです。
ブルーライトの少ない読書灯や電子書籍リーダーを使えば、リラックスしながら本の世界に入り込めます。
SNSや動画を見て夜更かししてしまうよりも、睡眠の質を高めながら知識も得られる、一石二鳥の習慣です。
通勤・通学時間を読書にあてる
電車やバスに揺られている時間は、意外と大きな読書チャンスです。
電子書籍アプリなら片手でページをめくれるので、荷物を持ちながらでも読めます。
仮に「往復で30分×20日=600分」と考えると、1ヶ月で10時間分の読書が自然に確保できる計算になります。
忙しい日常でも、朝・夜・移動時間といった「既にある時間」を見直すだけで、無理なく読書時間を確保できます。
「時間を作る」のではなく「時間をあてはめる」という意識が大切です。
スキマ時間とデジタルツールを組み合わせて活用する
「読書のために1時間まとめて確保しないといけない」と思うとハードルが上がりますが、実際には 1回5〜10分の積み重ねで十分 読書量を増やすことができます。
そのカギとなるのが、スキマ時間をデジタルツールと組み合わせる工夫です。
ここでは、すぐに実践できる具体的な方法を紹介します。
待ち時間は電子書籍でサクッと読む
病院やカフェでの待ち時間、通勤電車の移動など、「手持ち無沙汰」な瞬間は読書の大チャンスです。
スマホや電子書籍リーダーに本を入れておけば、SNSを開く代わりにすぐにページをめくれます。
たとえば、1日3回・各5分読めば、1か月で7時間以上の読書時間を確保できる計算です。
家事・運動中はオーディオブックで耳読書
「手はふさがっているけど、耳は空いている」時間は意外と多いもの。
料理や掃除、散歩やジムでの運動中にオーディオブックを流せば、作業がそのまま「学びの時間」になります。

読書アプリで習慣化・モチベーション維持
「続かない」という悩みには、読書アプリが役立ちます。
読書時間や読了冊数を自動で記録してくれるアプリを使えば、自分の進捗がグラフで見える化されます。
「今月は5冊読んだ」「1日平均15分読んだ」と数字で把握できると、モチベーションが上がり、自然と継続につながります。
スキマ時間をただの「空白時間」にせず、電子書籍・オーディオブック・読書アプリと組み合わせることで、忙しい毎日でも着実に読書を習慣化できます。
「読む時間がない」から「ちょっとした時間ならある」に視点を切り替えることがポイントです。
読書を継続するための工夫
読書は「始めること」よりも「続けること」が難しい習慣です。
最初はやる気があっても、途中で忙しくなったり、気分が乗らなくなったりすると、読書量は減ってしまいます。
ここでは、読書を無理なく継続するための工夫を紹介します。
読みたい本リストを作っておく
「次に何を読もうか」で迷うと、その間に読書習慣が途切れてしまいます。
事前に「読みたい本リスト」を作っておくことで、読書の流れをスムーズに保てます。
紙のメモでも、スマホのメモアプリでも構いません。思いついたときに書き溜めておくのがおすすめです。
読了後の小さなご褒美を設定する
人は「達成感」や「ご褒美」があると行動を続けやすくなります。
「1冊読んだらお気に入りのカフェでコーヒーを飲む」「週末は読み終えた本の感想をSNSに投稿する」など、小さな楽しみを組み込んでみましょう。
読書が「義務」ではなく「楽しみ」へと変わります。
SNSや読書会で仲間とシェアする
読んだ内容を誰かと共有すると、読書体験はより深くなります。
SNSで感想を投稿したり、読書会に参加したりすると、仲間から刺激を受けて継続のモチベーションが高まります。
「自分一人で続ける」より「仲間と一緒に続ける」ほうが圧倒的に長続きしやすいのです。
読書を継続する秘訣は、モチベーションを維持できる仕組みを作ることです。
リスト・ご褒美・仲間、この3つの工夫を取り入れることで、読書は日常の自然な習慣として根づいていきます。
今すぐ小さな一歩を踏み出そう
ここまで読んでいただき、読書時間を確保するためのさまざまな工夫をご紹介しました。
- 読書できない理由を把握する
- 毎日のスケジュールに小さな時間を組み込む
- スキマ時間とデジタルツールを活用する
- 継続のための仕組みを整える
読書時間は「特別に作るもの」ではなく、日常の中に自然と織り込んでいくものです。
大切なのは、知識を得ただけで終わらせず、今日から一つでも実行してみること。
例えば、
- 朝起きて15分だけ本を開いてみる
- 通勤中に電子書籍アプリを立ち上げる
- 家事の合間にオーディオブックを流してみる
どんなに小さな行動でも、積み重ねれば大きな成果につながります。
この記事を読み終えた今が、最初の一歩を踏み出す絶好のタイミングです。
ぜひ「今日からできる一つ」を選んで実践してみてください。